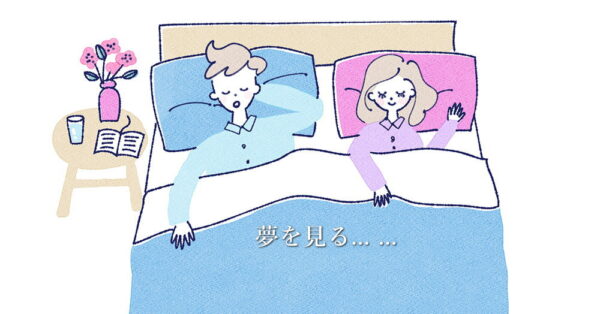
誰もが一度くらいは寝ている間の夢を見たことがあるかと思います。
日によって夢の内容をハッキリと覚えていたり、逆に夢を見ていたことは覚えているものの内容が思い出せなかったりすることもあるでしょう。
心地いい夢もあれば、いわゆる悪夢というものもあります。
こういった夢を見る原因と理由は一体何なのでしょうか?
ここでは改めて夢を見る原因と理由について触れていきたいと思います。
・覚えている夢の多くはレム睡眠のときのもの
睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があって、眠りが浅いのがレム睡眠、眠りが深いのがノンレム睡眠です。
目覚めたときに覚えている夢の多くは、眠りの浅いレム睡眠のときのものです。
実際にはノンレム睡眠のときにも夢を見ているのですが、ノンレム睡眠のときの夢は覚えていないことのほうが多いのです。
・夢を見る原因と理由は諸説ある
最近では質のいい睡眠を確保するためのアイテムもたくさん出てきていますし、睡眠についてはかなりの研究がなされています。
そのため、夢についてもいろいろとわかっていることがありそうなものなのですが、実は夢を見る原因と理由に関してはいまだにハッキリしていません。
夢を見る原因と理由に関しては、諸説あるというのが現状です。普段から人間はさまざまな情報を脳に蓄積しています。今は情報化社会ですから、昔よりもはるかに多くの情報を蓄積していることでしょう。
それらの蓄積した情報を整理するために夢を見るという話もあります。
つまり、脳内にある情報が睡眠中に処理されて、それがストーリーとなって映像化されたものが夢ということになります。
いろいろな情報がバラバラに組み合わされることによって、それが面白い夢になったり、不愉快な夢になったり、わけのわからない夢になったりするわけです。
・夢に関するさまざまな仮説
夢に関してはさまざまな仮説があるのですが、その中でも有名なのが20世紀の初頭にオーストリアの精神科医で精神分析学者でもあるジークムント・フロイトが唱えた説です。
フロイトは「夢は満足したいという願望の表れ」という説を唱えました。
この説では怖い夢ですらも、そこに何かしらの願望を映し出しているという解釈になります。
また、一方ではそのときの心理状態が夢に反映されるという説もあります。
例えば、仕事に追われているときには実際に何かから逃げるような夢を見ることもありますし、歯が痛いなというときに歯が抜けたり虫歯になったりする夢を見ることもあります。
さらに、寝る前に見たものが夢へダイレクトに反映されることもあります。
寝る前にスプラッタ系の映画やドラマ、アニメなどを見たときにそれがそのまま夢に反映されるということは珍しくありません。
だからといって、寝る前に好きなアーティストの映像を見ていたとしてもそれがそのまま夢に反映されるとは限らないので、夢というのは本当に奥深いものです。
あとは、予知夢といったものもあります。夢で見たものが現実に起こるというものです。テストで100点をとる夢を見たら本当にテストが100点で返ってきたということもあるでしょうし、人によっては自然災害の予知夢を見るといったこともあるでしょう。
本当に予知しているという見方もできますし、日常の些細なことに関しては夢で見た通りになるように無意識のうちに自分がそういう行動をとっているという考え方もできます。
・夢のコントロールはできる?
有名人の中には、夢をコントロールできると公言している方もいます。
いい夢を見ている途中で目が覚めてしまっても、もう一度眠ることによってその夢の続きを見ることができるというのです。
一部にはこのように夢のコントロールができる方もいるのですが、一般的には夢のコントロールは難しいと言われています。見ている夢の続きを見るのはもちろん、自分の見たい夢を見るのもかなりハードルが高いです。
いい夢を見たときには起きた瞬間にメモに残しておく、音声で残しておくといった形でとにかく内容を記録することで同じような夢を見られる可能性が高まると言われていますが、あくまでも可能性を高めるだけです。一応、ダメ元でも実践してみるといいかもしれません。
・良い夢を見たいなら寝る前にできるだけリラックスすること
自分の見たい夢ズバリそのものではなくとも、やはり少しでも良い夢を見たいところです。そのためには、寝る前にできるだけリラックスすることが大切です。
白湯を飲んで体を温めて、良い香りや優しい音楽の中でとにかく心身を落ち着けてリラックスさせましょう。
ストレッチなどで体をほぐしておくのも効果的です。
良い夢を見られる可能性が上がりますし、睡眠の質も改善していくはずです。
